【海峡両岸論】
国際政治から南シナ海紛争を読む
仲裁裁定と今後の中国外交
南シナ海紛争で、中国が管轄権を主張してきた「九段線には法的根拠がない」とする仲裁裁判所(写真1)の裁定(7月12日)が下った。北京は裁定受け入れを拒否したものの、噂された国際海洋法からの離脱はせず、南沙諸島の実効支配を維持・強化する一方、フィリピンと対話による関係改善を目指そうとしている。裁定内容を踏まえながら、南シナ海紛争を国際政治の文脈からとらえ直し今後を展望する。
(写真1)裁定内容を伝える同裁HPから

◆◆ 中国「完敗」の内容
裁定は英文で500頁からなり(1)中国が歴史的にこの海域や資源を排他的に支配していたとの証拠はない(2)中国の人工島造成は「サンゴ礁に甚大な損傷を与えた」(3)中国はフィリピンの油田探査や漁民のスカボロー礁での伝統的漁業権利を不当に妨害―などと違法性を認定した。中国の「完敗」は明らかである。
しかし同裁判所には領有権を判断する管轄権はなく、判決も主権には踏み込んでいない。従って7か所に上る中国人工島の領有権が否定されたわけではない。裁定が持つ拘束力とは何か。それは「人工島は島ではないから国際海洋法条約に基づく200カイリの排他的経済水域(EEZ)や大陸棚延伸の設定はできない」という点に尽きる。「九段線」の主張は元来、曖昧な内容だっただけに、「法的根拠が否定されたことで、中国も主張を引きずる重石がとれた」とみる中国研究者は少なくない。
フィリピンが仲裁手続きを求めたのは2013年1月。中国が前年の4月にフィリピン・スカボロー礁を奪ったことが契機だった。訴えの内容は〈1〉中国の「九段線」には法的根拠はない〈2〉中国の人工島は引き潮の時に露出する「低潮高地」か「岩」で、EEZや大陸棚の権利はない〈3〉人工島などの開発は、国連海洋条約の環境保護違反―など15項目に及ぶ。
提訴に対し中国側は「認めず、参加せず、受け入れず」の姿勢をとり続けてきた。理由は(1)中国フィリピン両国が合意した交渉による解決という二国間の取り決めに違反(2)中国は06年に国連海洋法条約に基づき、強制的紛争解決手続きの適用除外を宣言した(3)裁判所は領土主権と海洋境界画定問題について判断する権限はない―であった。裁定後も中国はこの姿勢を維持している。
裁定の詳細は次の通りである。〈1)中国は海洋環境保護に関する条約義務に違反し、埋め立てや人工島造成によって、生態系やサンゴ礁に取り返しのつかないほど甚大な損傷を与えた〈2〉中国は中国漁船によるウミガメやサンゴの密漁を容認〈3〉中国はフィリピンの油田探査や漁民のスカボロー礁での伝統的漁業権利を不当に妨害し、フィリピンの主権を侵害〈4〉中国公船は海洋の安全に関する条約義務に違反し、フィリピン船への接近を繰り返し衝突の危険を生じさせた〈5〉中国は、仲裁手続き開始以降も南沙諸島で大規模埋め立てによる人工島の造成を行い、仲裁手続き中に対立を悪化させることを避ける義務に違反―。フィリピンの主張がほぼ全面的に認められたことが分かる。
◆◆ 危うい沖ノ鳥島EEZの正当性
日本政府は「中国完敗」を絶賛し、裁定に従うよう北京に要求した。だが裁定は日本政府にとって見過ごせない内容を含んでいる。それは、南沙諸島に「島」は存在せず、中国、台湾、フィリピン、ベトナムなどが実効支配する「岩礁」は、200カイリの排他的経済水域(EEZ)を主張できないとする判断だ。
「島」の要件として裁定は「満潮時においても水面上にある」(海洋法条約121条第1項)に加え「人間の居住または独自の経済生活が維持でき」ること(同条第3項)を挙げた。国際紛争の争点になってきた「島岩論争」に、初の司法判断を下したのである。この判断に従えば、日本と中国、韓国の間で争いがある沖ノ鳥島(写真2)も単なる「岩礁」にすぎなくなる。「岩だからEEZは設定できない」とする中韓の主張を法的に裏付けるのだ。日本が大喜びできる内容ではない。
(写真2)沖ノ鳥島 東京都島しょ農林水産総合センターHPから

満潮時に、二つの小島が50センチだけ海面に頭を出す沖ノ鳥島がなぜ重要なのか。それは、日本の面積より大きい40万㎢ものEEZ設定できる経済的利益が絡むからだ。日本政府は1931年に同島領有を開始。戦後は米施政権下に置かれたが68年日本に返還された。国連海洋法条約を96年に批准した日本は、島の周辺200カイリにEEZを設定した。
しかし、満潮時に海水面に現われるのは2つの小島だけ。87年から約600億円をかけて防護壁の護岸工事を開始した。水没すればEEZを喪失しかねないと判断したためである。さらに「人間の居住または独自の経済生活」を可能にするため2005年から「海水温度差発電所」の建設実験を開始した。あの石原慎太郎元都知事が提言した計画だが、今日に至るまで発電には成功していない。つまり「人間の居住と経済生活」の維持という「島」の要件は今も満たしていないのだ。中韓両国は日本政府のウィークポイントを今後も突くだろう。
北京が、南沙と沖ノ鳥島を政治レベルで連動させたのは2015年8月である。王毅外相がASEAN関連会議で、中国の埋め立てを批判する岸田外相に反論、沖ノ鳥島の防護壁に触れ「他人のことを言う前に、自分の言動をよく考えるべきだ」と述べたのである。
昨年11月、筆者も参加した武漢大学国際シンポジウムで、台湾の大学教授が「中国側の埋め立て工事は、日本の沖ノ鳥島を先例として倣ったのだ」と発言したのを聞いて、少し驚いた。北京は公式には「模倣」と言ってはいないが、新華社通信が7月4日配信した記事は、日本の中国批判を「二重基準だ」と指弾している。「日本は南海島礁の属性を疑いながら、他方で沖ノ鳥岩礁の属性には口をつぐみ、依然としてEEZを設け漁船や船員を不当に抑留している」。さらに「日本は米国に追随して自由航行を鼓吹しながら、他国の艦船がトカラ海峡などの国際海峡を平常通り通過したことに怒り狂った」と批判した。漁船、船員の「不当抑留」とはことし4月、日本の巡視船がEEZ内で台湾漁船を拿捕したことを指す。
◆◆ 裁定拒否で両岸連携
台湾の蔡新政権は、台湾が実効支配する太平島を「岩」と認定されたことに憤り、「裁定拒否」で北京と足並みを揃えた。林全・行政院長は裁定直後の14日の行政院会議(閣議)で、裁定拒否の理由として(1)台湾を「中国台湾当局」と不当に呼んだ(2)太平島を岩とする法的認定は、台湾の南海諸島及び関連海域における権益を著しく損なう(3)裁定の過程に台湾を呼ばず、意見も聴取しなかった―を挙げ、「裁定にいかなる拘束力もない。政府は南海諸島を引き続き固守し、主権を守りいかなる妥協もしない」との強い姿勢をみせた。裁定後、海軍軍艦を太平島に派遣、漁民を上陸させたのも強い姿勢の表れである。蔡政権は馬英九前政権に比べ、主権の主張があいまいなため、裁定に対する姿勢によっては、北京と台北の対立要因になりかねないとの見方が大勢を占めていた。それだけに、北京にとって裁定がもたらした「両岸連携」は、沖ノ鳥島問題と並び予期しなかった「果実」と言えるかもしれない。
蔡政権の裁定に対する姿勢について台湾TVBSが行った世論調査(7月14日~18日)では、「蔡政権の処理に満足」が19%だったのに対し「不満」は45%に上った。また「蔡総統は主権を誇示するため太平島に上陸すべきか」との質問には賛成が69%に対し、反対は13%だった。台湾外交部が26日、月末に予定されていた日本との第1回「日台海洋協力対話」を当面延期すると発表したのも、政権に対する世論の厳しい目を意識したからとみられる。
◆◆ 矢吹新著の論点
裁定直前に出版された矢吹晋・横浜市立大名誉教授の『南シナ海 領土紛争と日本』(写真3・花伝社)は、紛争に関する拙論の不十分で曖昧な部分を正すとともに、歴史的経緯から国際政治上の意味まで、綿密な調査に基づいて分析・詳述しており一読をお勧めする。特に沖ノ鳥島の大陸棚延伸に関する部分は読み応えがあり、日本政府の主張の弱点がよく分かる。
(写真3)『南シナ海 領土紛争と日本』表紙 花伝社/刊
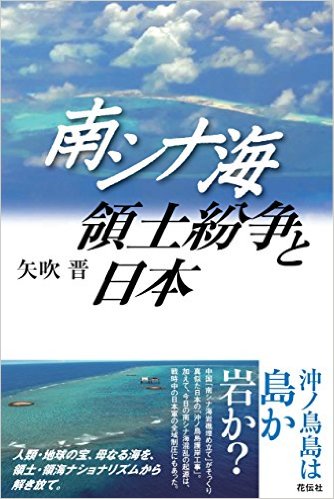
領土・領海ナショナリズムにとりつかれると、「あちら」の非ばかりに目を奪われ、「こちら」の行為には無自覚になる。これはどの国でも同じであり、沖ノ鳥島についても多くの人は日本政府の説明を鵜呑みにしてはいないか。さらに南シナ海の係争海域が、戦前は「新南群島」の名称で日本軍が支配していた事実を知る人は少ない。彼は、「紛争の源は日華条約で(新南群島の)帰属先を明示しなかったこと」と指摘する。尖閣諸島(中国名 釣魚島)と南シナ海紛争の発生の一因が、これら島嶼の帰属先の明示を拒んだサンフランシスコ条約にあることは明らかである。これはわれわれが十分自覚しなければならない歴史である。
矢吹はさらに「帝国主義による領土分割競争の戦後処理という要因が紛争の原点」とし「人類が経験した最も複雑な領有権紛争」と位置付ける。領有権については、各国の主張のいずれかを支持する立場には立っていない。「親中派」とみなされがちだが、「九段線」については、中国側主張を「終始曖昧な説明」と評し、懐疑的であることを紹介しておく。
現代中国を専門とする矢吹は、「尖閣問題の核心」(2013年、花伝社)をはじめ、計4冊の尖閣本を上梓しており、南シナ海紛争ではこれが1冊目。南シナ海問題と尖閣との関係についての彼の論点も興味深い。それは、尖閣国有化が中国に「二つの決断を下す契機を与えた」とし〈1〉東シナ海の大陸棚延伸を申請〈2〉沖ノ鳥島の教訓を模倣して南沙での埋め立てを強行―を挙げるのである。
さらに国際政治の文脈から「(南シナ海紛争が)中国脅威論を煽る材料としてしばしば利用され、ついに安倍内閣の安保法制成立への援軍として悪用された」と論じ、「国際法下の秩序」という「キレイゴトを前面に押し出す米国」が、いまも海洋法条約を批准しない矛盾を厳しく突いている。さらに「資源保護を優先させ、領有権争いを凍結した知恵」の重要性を説き、地域住民だけが利用できる共有材としての「ローカル・コモンズ」はなく、主権国家の管轄を超える「グローバル・コモンズ」を訴えているのは傾聴に値する。
◆◆ 国際政治から紛争を読むと
裁定は法的判断としては重要だが、南シナ海紛争の一側面にすぎない。国際政治と歴史など、総合的な角度からとらえなければ実相は見えない。南シナ海紛争の背景の一つが、米国と中国の新旧両大国による勢力バランス変化であるのは指摘するまでもない。韓国、台湾、東南アジア諸国連合(ASEAN)など、米国の旧来同盟国にとって中国が敵である時代はとっくに終わっている。言い換えるなら、冷戦時代に生まれた米国中心の同盟構造の軸は揺らいでいるのだ。同盟には「敵」が必要である。対中強硬姿勢を示すことによって、東アジアにおける指導的地位を確保するのが米国の目的であり、同盟の強化・再構築が急務である。
ここまで書けば、安倍政権こそ米国の意に最も忠実であることが分かろう。「中国の脅威」を理由に、集団的自衛権と安保法制の成立を急ぎ、自衛隊を米軍の「補完役」から「先兵」に変えるのが狙いだ。フィリピンとベトナムは、南シナ海で中国と対立はしていても、経済的な結びつきから中国を敵視してはいない。アジアインフラ投資銀行(AIIB)に、両国とも創設国として参加していることはそれを物語る。
仲裁裁判を国際政治の文脈からとらえ直せば、米国の安保上の既得権益を「法的に補強」するためであったと言える。北京は仲裁裁判所について、ハーグの国際司法裁(ICJ)や国連関連裁判機関ではなく、ハンブルグの国際海洋法裁判所の一部でもないとし「フィリピンが提訴した裁判のため臨時に設けられた機構」と、その「権威性」に疑問符を付けている。だがこれは主要争点ではないから、留意するにとどめる。
国際法の専門家は、仲裁裁定と国際政治の関係をどう見ているのだろうか。阿部浩己・神奈川大教授は7月30日、東京で開かれた「オルタ」主催の研究会で「ニカラグア侵攻で、米国はICJの判決に従わなかった。(中国が裁定に従わなくても)驚くべき対応とは言えない」と指摘した。ニカラグア問題とは1986年、米国がニカラグアの反政府武装組織を支援したとして同国政府が訴えた裁判。ICJは米国に3億7000万ドルの賠償を命じる判決を下したが、米国はICJに管轄権はないと主張、審理の大半をボイコットし判決に従わなかった。ICJと仲裁裁という違いはあるものの、中国が仲裁裁には管轄権がないとして審理をボイコットした点はよく似ている。
◆◆ ASEAN合意に今後のヒント
裁定に従わず強硬姿勢を続ける中国は今後どんな外交を展開するのだろうか? 阿部は「大国はだいたい判決には従わないが、結果的には判決を尊重する形で決着している」との興味深い指摘をする。ニカラグア紛争で言えば、1991年当時のニカラグア新政権は、米国からの援助の見返りに決着を図った。南シナ海紛争でも、この例に倣って中国が今後、フィリピンと二国間協議による話し合い解決の途を探り、結果的には200カイリのEEZを「棚上げ」して共同開発で合意するなど、裁定を「事実上受け入れる」可能性があるかもしれない。
7月末、ラオスの首都ビエンチャンで開かれた東南アジア諸国連合(ASEAN)外相会議では、裁定に対するASEANの対応が最大の焦点になった。共同声明は、中国による人工島造成などを念頭に「最近の動きに深刻な懸念」を表明したものの、仲裁裁定については一切言及しなかった。続いて開かれた中国とASEANの外相会議は共同声明を発表し、02年の「南シナ海行動宣言」の行動規範化の早期採択や「現在、人が住んでいない島や岩礁への居住」などを避け、紛争の悪化につながる行動を自制するとした。王毅外相は「行動規範」について「2017年前半までに枠組みの協議を終えたい」と述べた。法的拘束力のある行動規範の策定時期について、北京が明示したのは初めてである。
朱建栄・東洋学園大教授は「中国とASEANが、これ以上の埋め立て移住はしないことで合意した内容だ。フィリピンとベトナムもその点を確認した上で、仲裁問題で中国を非難しない共同声明に同意したのだろう」と読み込んだ。このあたりに、中国の今後の動向を占うヒントがあるようだ。
◆◆ 米中対立は「出来レース」
中国反応で注目されるのは、非難の矛先を安倍政権に集中している点だ。それは対米非難に勝る。「テロとの闘い」に高い優先順位を置く米国にとって、折から発生した「ニース・テロ事件」やトルコのクーデター未遂、韓国への高高度防衛ミサイル(THAAD)配備決定のほうが、南シナ海紛争より明らかに優先度が高い。その分、安倍政権が中国非難の急先鋒に躍り出た印象が突出し、それに中国が反論・対抗する構図が鮮明化しているのだ。
地球規模の経済的利益を共有する米中両国は、南シナ海での軍事衝突(写真4)は全く望んでいない。米国が進める「航行の自由作戦」では確執が目立つが、実際は「出来レース」の側面が強い。南シナ海紛争に対する米国の基本姿勢をみればその理由が分かる。「対中強硬姿勢を示すことによって、東アジアにおける指導的地位を確保する」のが目的であり、仲裁裁判は「米国の安保上の既得権益を法的に補強するため」。「航行の自由作戦」もこの目的達成のため、ASEAN諸国に「米国の指導力」を見せる、ある種の「演技」と言ってよい。中国もそれを理解しているから、反応には自制がみられる。
(写真4)米「航行の自由作戦」を報じる「産経」号外

裁定後も米中両国は、政府間ハイレベル協議と軍事対話・交流を積み重ね、米国は「自制」している。7月12日裁定からの1カ月をみても▼米海軍制服組トップのリチャードソン作戦部長が7月18-20日初訪中し、呉勝利海軍司令官と会談(同作戦部長は26日、ワシントンで、呉司令官との会談で、中国が南シナ海で防空識別圏を設定し、スカボロー礁で施設建設を継続すれば、米中関係に悪影響と懸念表明したと説明)▼習近平国家主席は7月25日、訪中したライス米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)と会談、「現行の国際秩序や規則に挑戦するつもりはない」と対米協調姿勢をアピール▼米太平洋軍は8月8日、太平洋艦隊のスコット・スウィフト司令官が中国海軍北海艦隊の拠点がある青島を訪問し、袁誉柏司令官と会談したと発表―。
中国としては、米大統領選挙の行方を見定めながら、外交駆け引きによって東アジアでの「米国の指導力」を一定程度満足させる妥協点を探るとみられる。
◆◆ 前のめりの日本、「ハシゴ外し」も
当事者であるフィリピンのドゥテルテ政権も、6月末の就任後は中国を刺激する言動は一切控え、対話に向けた環境整備を模索する。大統領特使のラモス元大統領(写真5)を8月8日に香港入りさせ、今後の交渉に向けた地ならしを開始。11日には中国外務次官を歴任した全人代外事委員会の傅瑩主任と会談した。さらに12日、滞在先の香港で記者会見し、「適切な時期に中国政府と公式協議を行うことを望む」と表明、平和的解決に向け、対話の継続を目指すドゥテルテ政権の意向を強調した。中国も香港入りを歓迎している。
(写真5)ラモス元大統領(wikipedia から)

目立つのは、裁定を中国脅威論の材料として前のめりになっている安倍政権である。岸田文雄外相は8月11日、ドゥテルテ大統領と会談、中国への結束対応を呼び掛けた。しかし「対中包囲網」を築きたい日本と、中国との経済関係を重視し対立激化を避けたいフィリピンとの温度差が逆に浮かび上がる結果となったようだ。前述したように、フィリピンもベトナムも、「反中同盟」に加わり中国を敵視する気は一切ない。ドゥテルテは岸田に、中国に仲裁判断の尊重を求める考えを示したが、岸田に同行した外務省筋は「リップサービスの要素もある」と神経をとがらせたという。
裁定直後の15日、モンゴルの首都ウランバートルで開かれたアジア欧州会議(ASEM)の際の日中首脳会談で、安倍首相は「法の支配を重視し、力による一方的な現状変更を認めないとの原則を貫くべきだ」と主張。これに対し李克強首相は「日本は当事国ではない。言動を慎み、騒ぎ立てたり干渉したりしてはいけない」と強く反論した。さらにラオスのASEAN外相会議に向かう岸田が24日「法の支配の重視、平和的解決の大切さを訴えたい」と、仲裁判断に従うよう中国に促すと、中国がかみついた。外務省の陸慷報道局長は「日本は当事国でない。(日中戦争の)不名誉な歴史もある。あれこれ言う資格はない」と岸田非難のコメントを発表するのである。
日本政府が過剰介入を続ければ、引くに引けない状況に陥り、場合によっては「ハシゴ外し」に遭う恐れすらある。中国は今後、沖ノ鳥島問題で日本に揺さぶりをかけるほか、米国の「航行の自由作戦」に対抗して、中国軍艦が日本領海を通過する中国版「航行自由作戦」を展開する可能性がある。中国海軍の情報収集艦が6月に鹿児島の口永良部を通過したのはまさにその一例であった。5日から、沖縄県・尖閣諸島周辺海域で多くの中国公船や漁船が航行し、日本側の抗議で外交問題に発展した。在京中国外交筋は「8月1日の禁漁解禁で中国漁船が例年より大量に出漁し、監視に当たるため大量の公船が航行したもので偶然」と強調する。しかし時期から判断すると「仲裁判断を巡る日本の対応に反発した可能性は否定できない」(日本政府筋)との憶測は消えない。
尖閣諸島(中国名 釣魚島)問題以来、アジアで燃え盛る領土ナショナリズムをいかに鎮めるか。南シナ海は米国の湖でも中国のものでもない。そこで生きる住民の生活海域だ。国民国家の枠組を超え、共同管理・開発で共通利益を目指す思考を持たないと、領土ナショナリズムの魔力にはまるだけである。
(共同通信客員論説委員・オルタ編集委員)
※この記事は著者の許諾を得て海峡両岸論第69号から転載したものですが文責はオルタ編集部にあります。