【海峡両岸論】
台湾人意識の深層を解剖
『台湾と尖閣ナショナリズム』を推す
中国の大国化とともに、台湾で「台湾人アイデンティティ」が強まっている。多くの民意調査の結果はそれを裏付けているし、台湾独立を党綱領にうたう民主進歩党(民進党)政権の誕生を、台湾人意識の文脈から説明するメディアも多い。台湾海峡両岸の経済・社会が一体化するにつれ、中国共産党に対する忌避反応が顕在化し、それが台湾共同体意識を育んでいると思う。
同時に大多数の台湾人は中国・福建を原籍とする「中華民族」である。台湾人意識の強まりを、非中国化の「不可逆的な過程」と見做すのは正しいのだろうか。筆者(本田)は尖閣諸島(台湾名 釣魚台)をめぐる領有権争いで「稀に動きがあった時、台湾社会が見せる微妙な揺れは、『親日台湾』の根底に普段は見えにくい何かが存在することを感じさせる」と書く。「見えにくい何か」とは、台湾人の深層意識にある「中華民族意識」である。
その解剖は、台湾と台湾海峡の両岸関係を展望する上で欠かかせない作業だ。筆者は25年間にわたって住み続ける台北をベースに、台湾と大陸に香港と、中華世界全体を取材するフリージャーナリスト。既に『中国 転換期の対話—オピニオンリーダー24人が語る』(岩波書店)はじめ、幾つかの優れた著作をものにしている。
(写真1)『台湾と尖閣ナショナリズム 中華民族主義の実像』(本田善彦/著 2016年4月 岩波書店 208頁 税込2,592円)
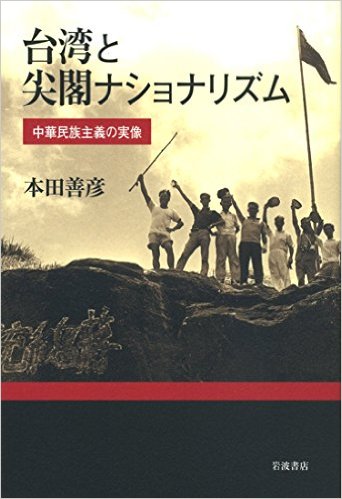
◆◆ 台湾が尖閣問題の発火点
本書を貫く問題意識は、表層にある「台湾人意識」と深層に横たわる「中華民族意識」の関係だが、それにとどまらない特徴がある。第一は、尖閣問題の発火点が中国大陸ではなく、台湾だったことを当時の活動家のインタビューから丹念に掘り起こした。1970年9月、尖閣周辺で台湾漁船が日本側に駆逐された事件が、在米の台湾人留学生の怒りに火をつけ、今も続く東シナ海での領土紛争の起点になったのである。
筆者は尖閣防衛を叫ぶ「保釣」運動の活動家の目から、台湾社会の変化と「運動の背後に横たわる社会意識」を解剖する。運動を担った当時の在米留学生・研究者の中には、馬英九前総統をはじめ、台湾政界をはじめ学界、言論界を中心に台湾エリートがキラ星のようにいた。
例えば、李登輝時代の行政院スポークスマンを務めた玉銘。陳水扁政権下で駐日経済文化代表処の代表になった羅福全や李遠哲・元中央研究院長もそうだ。蔡英文政権の外交部長に就任した李大維は学生組織のリーダーだった。そのことは保釣運動が、統一派と独立派や左右の立場を問わず、国民党独裁下にあった当時の台湾のエリートの多くが反応し、盛り上がりを見せたことを示している。
やがて米国でのデモは台湾本土に伝播し、1971年4月には台湾大学を中心とする青年が日本大使館や米国大使館に向けて「戒厳令下で初の街頭デモ」を敢行した(写真2)。しかし台湾を取り巻く国際情勢は急変する。その年の夏、ニクソン米大統領が訪中すると発表したのに続き、秋には中華人民共和国が国連代表権を獲得し、台湾は脱退した。
(写真2)1971年4月、ワシントンでデモする台湾留学生。清華大学図書館収蔵

◆◆ 権力監視する改革運動に転化
第二に「保釣」運動の変化である。中国大陸では文化大革命の最中で、在米留学生たちの左傾化が進む一方、学生たちの関心は釣魚台から民主に転化した。彼らが既に70年代初めに「中央民意代表全面改選」を要求していたことを本書で初めて知った。筆者は「保釣運動は領土認識や歴史観にとどまらず、台湾知識人の精神構造に深遠な影響を残した」とみる。運動に参加していた当時の学生は「70年以降、台湾で発生した変化を振り返ると、保釣は全ての始まりだった」(林戴爵)のであり「民主化を語るにあたり、70年代の保釣運動はルネッサンスにも等しい重要な契機」(銭永祥)だった。ナショナリズム運動がやがて、政府批判へと転化する典型である。
筆者は「70年代の北米や台湾での運動は、やがて国府に対する懐疑や、批判を伴い、社会改革への力として昇華」したと位置づけ「それと類似した流れが大陸でも発生している」と指摘する。「保釣」運動が大陸で高まるのは2004年からだが、その中心的活動家の李義強は、常に当局の監視対象になり、これまで4回、厦門から尖閣に向けて出港するたびに当局から阻止されたという。日本では、尖閣上陸を中国政府が支援しているとの俗説が流布しているが、それを否定する証言でもある。
◆◆ 優越と劣等が交錯するコンプレックス
第三は、台湾人意識とナショナリズムの関係だ。「台湾本省人のアイデンティティの在り方は世代ごとに異なっていたかもしれないし、社会階層の格差から家庭ごとにそれぞれ異なるアイデンティティがあったのかも」とし、固定的ではなく動態的だとする。大陸活動家の李義強は「愛国」を「国家の体制ではなく両岸そして世界の華人にとっての共通の価値である中華民族が念頭」にあるみる。
また米国留学中の71年、中国大陸に行き周恩来と面談した台湾映画監督の王正方は「私にとっての祖国は中国の伝統文化だ。民進党、国民党、共産党の言うところの国家とは政権、すなわちシステムにすぎず、アイデンティティを感じるに値するものではない」と語る。さらに当時、香港から台湾に留学していた週刊誌「亜洲週刊」編集長の邱立本は、中国人アイデンティティを「優越感とコンプレックスが重層的に交錯する植民地社会の複雑な心理」と表現した。
筆者の「複雑な心理」を解析する筆致は冴えわたる。台湾と香港では2014年春と秋に学生を中心とする「ひまわり運動」と「雨傘運動」が燃え盛った。「雨傘」にみられる香港人の意識を筆者は「香港返還から時を経て、香港がかつて大陸に誇った優位性の多くが消え去り、香港住民の中には中国全体への拒否反応も見られ」と書き、これは「民族意識の変化というより、現実的な政治環境に対する選択の結果」とみる。
(写真3)2012年8月15日、魚釣り島に上陸した香港活動家/中国CCTV画面から

◆◆ 「偏安」と「避秦」
長く植民地支配を受けた人々の意識にある旧統治者と現統治者に対する優越感と劣等感が複雑に絡み合った感情から、深層にあるナショナリズムをあぶりだすことは可能だろうか。筆者はその回答として「偏安」と「避秦」というキーワードを用意する。転変する中国史を理解する上で重要な用語だ。「偏安」は「支配する国土を奪われた統治者が、地方に落ち延び残された領地を支配し安逸を願う」ことだ。台湾になぞらえれば「日米の庇護の下、ひたすら自己保全を願い—被害者意識を募らせる—敗北主義的心理、台独のそれと多くの点で酷似」と、興味深い解説を筆者は試みる。
一方「避秦」は「中原への記憶や願望が希薄、もしくは存在せず、自己保全に向け、外部の強権から回避しようとする本能」である。日本植民地時代は「大陸が外国と化した現実の中、日本との同化が進む一方、日本との違いを自覚させられたことに伴い、自らのよりどころとして中原が再び意識される」。
これを現在の台湾の社会意識で説明すれば、「ひまわり運動」には「避秦的心理」(大陸からの逃避志向)が見える。また台湾人意識が高まる一方、台湾の将来については「現状維持」が常に主流民意になる説明にもなる。筆者は「現状維持」というモラトリアムのような社会心理は、「偏安」と「避秦」が「絡み合って成型された思潮」と読み説く。この比喩と分析を咀嚼するのに、すこし時間がかかった。
◆◆ 台湾は「親日」という傲慢さ
8年に及んだ馬英九政権に替り蔡英文政権が誕生すると、日本メディアではまた「反日から親日へ」というステレオタイプな論調が独り歩きしている。ヘイトスピーチにみられる排外主義的な敵対ナショナリズムに対し、「親日」「反日」という日本への距離感から相手を評価する観点を評者は「日本誉めナショナリズム」と名付けている。ヘイトスピーチが攻撃的であるのに対し、「日本誉め」は内向きだが、本質は全く同じである。「親日台湾」のイメージもそうした心理の反映であり、旧植民地の被支配者に対する傲慢な視線に溢れている。
本田もその見方を共有する。「筆者も日ごろ台北に暮らす中で、台湾に対する一部日本人の態度について『上から目線の同情や親近感は珍しくないが、敬意は相対的に薄くしかもそれに無自覚なことが多い』と感じる」と書く。台湾人を「恣意的に利用が可能な他者」とする見方でもある。
尖閣問題が炎上した2012年の8月、尖閣に上陸し五星紅旗を掲げた元香港立法局議員の曽健成は決して「親中派」ではない。雨傘運動を強く支持した活動家でもある。その彼が中国国旗を掲げた心理を筆者は「香港に生きる者の自尊心、これらを絶妙のバランスで結びつけるものが、日本という他者を介して意識される中華民族意識」と分析した。中国共産党は嫌いでも彼らにとって、それは「身内」なのであって、日本は「他者」であることを忘れてはならない。
「『国家』『民族』の大義を掲げる運動は〜中略〜実はけっこう楽しいのではないか、精神的な何かを満たすものではないか、と感じることがあった」と筆者は告白する。その通りだ。普段は他者から顧みられることが少ない我が身を、国家の「大義に殉じる」ポーズをとることで、正義を背負った気になるネトウヨ諸君にも通じる意識だと思う。SNS世代の一部に浸食する、内向きでジメッとしたナショナリズムの心理だ。
(評者は共同通信客員論説委員・オルタ編集委員)
※この記事は「21世紀中国総研」第68号(2016.06.25発行)から筆者の承諾を得て転載したもので文責はオルタ編集部にあります。