【海峡両岸論】
衰退ニッポンに響いた「戦略的親日」
~両岸緊張させた「プリズム政治家」
台湾の李登輝元総統(写真)が7月30日、97歳で死去した。国民党の一党支配に幕を引き、民主化を進めた「民主の父」と絶賛の声がメディアでは目立つ。しかし米中、日中対立に乗じ、日米との安保協力によって中国との対決を煽り、台湾海峡情勢を緊張させた責任は小さくない。北京は「両岸関係破壊の元凶」「中華民族の罪人」(環球時報)と批判し、評価は180度異なる。言説に矛盾の多い人物だったが、日本語を流ちょうに話し日本を知り尽くした知識や人柄が、多くの日本人を引き付けたのも事実である。「日本精神」や「武士道」を評価する「戦略的親日」は、衰退し自信を失った日本人の心に響いた。単なる「民主の父」でも「親日」でもない。多面的な顔を持つ稀代の「プリズム政治家」だった。
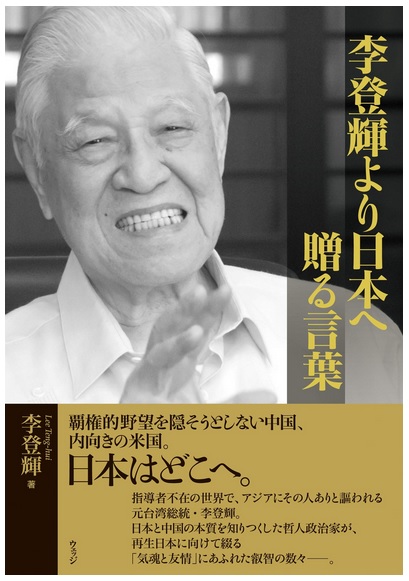
『李登輝より日本へ 贈る言葉』表紙
◆ 日本人の思考方法、欧米の価値観
「李は不思議な人である。台湾人の心を持ち、日本人の思考方法と欧米の価値観を持つ。同時に中国的な社会、文化背景の中で生きている」
台北に駐在していたちょうど20年前、当時の陳水扁政権に近い古参ジャーナリスト、司馬文武(江春男)氏からこんな「李登輝論」を聞かされたことがある。「台湾人の心」はよくわかるが、その他の形容については説明が要るだろう。
李は日本植民地時代の台湾に「日本人」として生まれ、1945年の日本敗戦の22歳まで「日本人だった」。多感な青年期を京都帝国大で学んだから「日本人の思考方法」が血肉化されたと考えていい。台北郊外の自宅では、曽文恵夫人と日本語と台湾語を混ぜながらしゃべっていた。
「民主」「自由」「人権」に代表される「欧米の価値観」の説明は要らないと思う。総統就任(1988年)後、90年代初めから立法委員(国会議員)の終身議員制を廃止して全面改選し、間接選挙だった総統選挙を直接選挙に移行(1996年)させたことを挙げれば十分だ。
◆ 共産党顔負けの権力闘争
だが、「台湾人の心」を持つ彼が「中国的な社会、文化背景の中で生きている」とはどういう意味か。敗戦後台湾に戻った李は、台湾共産党の地下活動に参加。その後大学教員や農業技師を経て、70年代初め行政院長だった蒋経国(後に総統)に見出され政治の世界に。国民党一党支配下で台北市長、台湾省主席などキャリアを積み上げていく。
総統に就任してからは、熾烈な権力闘争で政敵を次々に粛清し、権力基盤を強化していった。共産党顔負けのその手練手管は、「中国的な社会・文化背景」を体現していなければできない芸当である。
両岸関係では、1991年「中国大陸と台湾は均しく中国であり、一つの中国の原則に基づいて敵対状態を解除して統一に向けて協力する」という内容の「国家統一綱領」を定め、92年には民間交流窓口を創設し、両岸の経済・民間交流推進の基礎をつくった。その一方、退任直前の99年には「台湾と中国は特殊な国と国の関係」と位置付ける「二国論」を提起し、両岸関係の緊張を激化させた。
江沢民時代の中国に複数の「密使」を送り、当時の国家主席だった楊尚昆らと接触させ、米国製武器の購入計画や1995年の訪米計画を、事前に北京に通知、両岸関係の緊張激化を避けようとする権謀術数も発揮した。
こうしてみると李登輝は、光が差す角度によってさまざまな色に変化する「プリズム」のような人物のように思える。オランダ支配から清朝、日本植民地から中華民国へ―。支配者が転変した歴史を振り返れば、李登輝世代の台湾人が複合的アイデンティティを持つのは当然だった。
◆ 「戦略的親日」とは?
彼に必ず貼られる「親日」のレッテルは、正しいのだろうか。
多くの日本人にとって彼の魅力は、九州訛りの日本語を操りながら、戦前の日本を最大限ほめそやす「親日イメージ」にある。日本人が口にできない、植民地支配の過去を否定せず、「台湾近代化に多くの貢献をした」と、肯定的に評価してくれる存在だった。
実兄が祀られている靖国神社を自ら参拝(2007年)した。靖国神社問題を「中国とコリアがつくったおとぎ話」(同)、「中国という国は南京大虐殺のようなホラ話を世界に広め」(2014年)などと、中韓による日本批判にも「反論」してくれた。
総統退任後は計9回訪日したが、7回目の訪日(2015年7月)時には、日本の雑誌に寄稿し「日本と台湾は『同じ国』だったのである。『同じ国』だったのだから、台湾が日本と戦った(抗日)という事実もない」とし「当時われわれ兄弟は紛れもなく『日本人』として、祖国のために戦ったのである」と書いた。植民地支配下にあった台湾を「国」と呼ぶのはどうかと思うが、ひとまず置く。
◆ 「ニッポン」を肯定する光
李は常々、外来支配の下で「主人公」になれない台湾人を「台湾人の悲哀」と表現した。だが、ここでは植民地支配者の日本を「祖国」と呼ぶ。英植民地だったインド人や香港人、マレー人は、英国を「祖国」と呼ぶだろうか。朝鮮半島の人たちが日本を「祖国」と呼んだ例を知らない。
日本を「外来政権」と呼ぶ一方で、「祖国」と表現する矛盾。持論の「日台運命共同体」を強調し、北京への挑発を十分計算し尽くした「戦略的」発言である。台湾、朝鮮植民地支配の歴史を清算できない日本の右翼政治家をくすぐる。
李発言に「感応」するのは右派だけではなかった。歴史認識をめぐる中国や韓国の日本批判に「疲れた」日本人が、「外国人」である李の発言を聞き、過去の歴史と自己を重ね合わせた「ニッポン」を肯定する「光」を見出したのだと思う。
「日本人の思考方法」を知りつくした「戦略的親日」は、十二分に威力を発揮した。「戦略的親日」は、日本世論に「親日か反日か」の二分論思考を流行させ、「中国敵視」の市場を拡大する触媒作用も果たした。
◆ 共振する二つのナショナリズム
それは戦後、日本人が自制してきた「ナショナリズム」を刺激する効果ももたらした。その背景には、①日本が衰退期に入り自信喪失が顕在化、②巨大化する中国への脅威感の高まり―を挙げねばならない。
反中ナショナリズムは、中国の「統一攻勢」と「軍事的脅威」にさらされている台湾への同情と「親台」意識も生み出した。日本で芽生えた「ナショナリズム」は、中国と韓国、北朝鮮を敵視することによって成立する「敵対的ナショナリズム」である。
一方の台湾。李による民主化と政治の台湾化は、「台湾アイデンティティ」を強めただけではない。台湾を中国から切り離し、非中国化によって統一に反対する「台湾ナショナリズム」を煽った。
日本における「親台」と。台湾の「親日」は、いずれも「反中国」の旗を掲げるナショナリズムとして共振し合ったのである。
◆ 矛盾に満ちた言説
「(李の)言説には矛盾が多い」と書いたが、具体例を挙げよう。「二国論」提起以来、中国は彼を「台湾独立派」の頭目と非難し続けてきた。しかし本人は「一度も独立とは言っていない」のを口癖にしてきた。台湾は主権独立国家だから、「独立を主張する必要はない」という意味である。
2004年12月、数人の日本人記者とともに彼の私邸(写真)に呼ばれ懇談する機会があった。その時、李は問われもしないのに、「サンフランシスコ平和条約」(1951年)で日本は台湾の主権を放棄したが、帰属先を明示しないため「帰属は未定」とする「帰属未定論」を展開した。「今の台湾は、米軍制下にあるイラクと同じですよ」と繰り返すのだった。これは「帰属先は未定だから独立宣言しなければならない」という伝統的な台湾独立派の主張だけに、「えっ、こんなこと言うのか?」と、いぶかしかったのを思い出す。

2020年1月14日 97歳の誕生日に私邸を訪問した蔡英文総統と李~自由時報より
もう一つは尖閣諸島(中国名 釣魚島)発言。総統退任後の2002年、彼は沖縄紙とのインタビューで、「沖縄県に属する日本固有の領土」と初めて発言し波紋を広げた。その後も来日するたびに「日本領土」と繰り返してきた。
もちろん現職の総統時代、そんなことを言うわけはない。かつて秘書役を務めた人物は筆者に対し、李が副総統時代に「尖閣は中国領」と主張した著名な日本人学者の書籍を、彼を通じて日本から取り寄せたと聞いた。「中華民国領」の根拠を補強するための「理論武装のためです」と、元秘書役は言っていた。
ついでに言えば、先の「『日本人』として祖国のために戦った」との言説は、台湾でも問題視されたが、同じ2015年、台湾の大学生に向けた講演では「(台湾人が)日本人の奴隷になったのは悲しい」と述べている。時と場所によって、発言内容はくるくると変わる。
◆ 米日連携で中国と対抗
李が台湾独立色をより鮮明にするのは総統退任後である。少数与党だった民主進歩党の陳水扁政権が、国民党員を行政院長(首相)に据え「全民政権」としてイデオロギー色を自制したのに対し、李は「中華民国は国際社会で既に存在していない。台湾は正名を定めるべき」として「台湾正名運動」の責任者に就任。2001年には独立派を中心とする「台湾団結連盟」を結成した。
中国の台頭で米中対立が激化し、歴史・領土問題を契機に日中関係も悪化する中、李は米日との連携を強化して、中国の統一攻勢に対抗するよう民進党政権に働き掛け続けてきた。輸出の4割を中国に頼り、経済依存関係を深める台湾にとって、中国との安定した関係は生存の必要条件である。
両岸政策では「統一」はもちろん「独立」も選択できない台湾には、中国との安定した関係維持には、「現状維持」しかない。だが「現状維持」政策には、台湾の将来に向け具体的な展望や出口を提示する力はない。
第2期に入った蔡英文政権が、第1期には強調した「現状維持」路線から離れ、中国を敵視し、米日軍事連携を説くことによって支持率を維持する姿勢を見ると、皮肉なことに李路線を継承しているかのように見える。
◆ 「おごり」と「甘え」
李の「戦略的親日」は、日本人に「おごり」と「甘え」をもたらした。その例を挙げる。麻生副首相兼財務相は外相だった2005年2月、国会答弁で「台湾の教育水準が高いのは、植民地時代の日本義務教育のおかげ」と発言した。これに対し、当時の陳水扁政権の外交部スポークスマンは「教育も植民政策の一環であり、目的は誰もが分かっている」と、植民地統治の正当化に反発した。これが「親日」といわれる民進党政権の植民地統治に対する公式見解である。
かつての宗主国のリーダーが、植民地統治を正当化する言説を公言するのは稀だ。植民地支配を受けた側がこの言説に与するのは、自殺行為である。このスポークスマン発言に「反日」のレッテルを貼れるだろうか。「戦略的親日」に寄りかかり、植民地統治を正当化する麻生の「おごり」と「甘え」こそ、問題にしなければならない。
もう一つ例を挙げよう。2002年、台湾の性風俗業や買売春を、写真入りで紹介した日本のムック本『極楽台湾』が、台北で販売禁止される事件が起きた。当時の台北市長は馬英九。この時『極楽台湾』を取り締まった馬英九を「反日」の一言で、ばっさりと切り捨てた中国研究者もいる(「胡錦濤より『色男』で『反日』の馬英九」 「諸君」2005年3月号)。
「反日」のレッテルだけではない。傑作なのは結論部分で、この研究者は「李登輝に代表される日本語世代のような、無条件に日本を愛してくれた親日派は、今後急速に消滅していく」と書く。李は多くの台湾人同様、複合的なアイデンティティを持つと同時に、極めて現実的な政治家だ。「無条件で」宗主国を愛するような政治家がいるとすれば、その資質が疑われる。研究者の見立てもまた、「戦略的親日」に騙された結果、産み出された「甘え」と言わざるを得ない。
◆ 「現状維持」の岩盤は割れず
李登輝は、政治的には「過去の人」であり、その死が国際政治に与える影響は限定的である。安倍信三首相は31日、官邸の「ぶら下がり」で、「台湾に自由と民主主義、人権、普遍的価値を広めた」と功績をたたえ、「常に日本に特別な思いで接してこられた。日台関係の礎を築いた方として、多くの日本国民は格別の親しみを持っている」と述べた。国交のない台湾元リーダー対する最大級の弔辞である。
安倍が言うように、今世紀に入ってから、大地震や水害など自然災害時の人道支援を契機に、国交のない日台関係は「官民」ともに緊密化した。李の「戦略的親日」の成果と言っていいだろう。
中国の巨大化と米中対立激化の中で、「台湾人意識」が高まり、特に香港大規模デモを契機に、世論調査では「台湾独立」への支持も増えている。しかし李登輝が果たせなかったものがある。それは「一つの中国」を前提に成立している「中華民国憲法」下の「中華民国体制」を崩すことである。
台湾で「一つの中国」はどんどん有名無実化しているとはいえ、その岩盤を崩すのは容易ではない。蔡政権が公約にする「現状維持」とは、北京に向けて「中華民国体制」を維持し「独立」しないというサインでもある。
「皮一枚」でつながっている中華民国体制を崩せは、北京は「反国家分裂法」に基づき台湾独立とみなし、「非平和的手段」(武力行使)の選択を迫られる。北京も台北もそして中国叩きを加速するワシントンにとっても、決して見たくないシナリオである。
権謀術数に長けた李登輝だが、「現状維持」という堅い岩盤は割れなかった。
(共同通信客員論説委員)
※この記事は著者の許諾を得て「海峡両岸論」117号(2020/08/02発行)から転載したものですが文責は『オルタ広場』編集部にあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧