【オルタ広場の視点】
新聞記者が政治家になる事例をたどって
――朝日新聞出身者の130年を見る
こんなことを調べて、何になるのか?
みずからそう思いながら、かなりの時間を費やして、首をかしげつつパソコンを打っている。きっかけは、酒飲み話に「最近は新聞記者出身の政治家はいなくなったなあ」「かわりに、テレビ出身組が増えたよ」「なに、大型の政治家が出なけりゃ、つまらん」といった会話があり、つい「調べてみようか」「やれよ、案外面白いぞ!」などと踊らされての作業になった。
というわけで、長い原稿にはなったが、べつに大した論理性や分析の帰結があるわけではない。まあ、関心があれば、故郷の選挙区、同世代、何をやっていたか、などをサラーリと目で追っていただければ幸い、というものだろう。
ただ、それだけだと、芸もないので、もっともらしい指摘でもしてみたい。
毎日には保利茂、安倍晋太郎、竹内黎一、高木陽介、大島理森、鈴木恒夫、高原寿美子、川島正次郎、坊秀男、山下春江、鈴木茂三郎、加藤高明ら、読売には正力松太郎、池田禎治、池田正之輔、細川嘉六ら、日経に田中六助、東京に青木正、近藤昭一(中日)、産経に前田久吉、長谷川仁、額賀福志郎、松波健太、形だけながら森喜朗ら、の各社出身の政治家もいる。
ここでは最多の朝日新聞社にとどめた。
*時代的な数は? 戦前は衆院で27人、貴族院(勅選)3人の計30人。戦前から戦後に足をかけた者は衆議・貴族両院2人、衆院8人、衆・参両院が1人、で計11人。そして、戦後は衆院10人、参院8人、衆・参両院1人の計19人。合わせて60人にのぼる。
*戦前に多かった「腰掛組」 明治、大正、昭和前半の新聞記者は、あちこちの新聞社を転々とするケースが多かった。新聞社の数も多く、小規模経営で倒産、合併などの離合集散があったり、待遇面や仕事の内容次第で選別したりするケースも少なくなかった。今どきのような、厳しい入社試験もなく、学校や同郷などの関係での入社も多かったようだ。
もちろん、新聞記者一筋といった若者たちもいたが、将来の「政界入り」のために政界を知り、政治家周辺のコネを求めるための記者志望も少なくなかったことが読み取れよう。
*尊重された外遊組 戦前は、学校を出て、欧米に留学したり、中国に渡って言葉と当地の実態を知ろうとしたりした若者が、新聞社に必要な時代だった。国際化のスタートの遅かった日本の新聞社として、グローバルに欧米、アジア事情に通暁する必要があり、とくに軍事的侵出の進む中国や朝鮮に詳しい記者を集めたかった。昨今以上に、特派員を確保したい発展期の日本だった。
別表をたどると、欧米関係では石橋為之助、清瀬規矩雄、神田正雄、兼田秀雄らがいる。中国・旧満州がらみでは小西和、小山松壽、一宮房治郎、石川安次郎、神尾茂らがおり、橋本登美三郎もその一員だったのだろう。
*新聞社の欲しい著名人 戦争の頻度増、長期化、拡大に伴って、情報源としての新聞が次第に必要視されていく。新聞社も、情報の多角化、速報化、信頼度が強く求められるようになり、優れた記者と同時に、社外からの既成の著名人や文筆家、学者たちが必要になる。
外部に求められた人材は多く、そのうち政治がらみの人物が末広重恭、杉浦重剛であり、のちの下村海南、前田多門だった。ほかにも、朝日という新聞社だけ見ても、著名だった人材は多く存在したし、各紙共通の課題でもあった。朝日には、夏目漱石、石川啄木をはじめ数え切れない人材が関わって、それが新聞という存在の信頼につながった。
新聞社の財産が「ひと」だという認識が弱まり、新聞人がおのれの存在に自信を持たなくなった時に、報道は大きく崩れていく。毎日新聞が歴史的なダメージを受けた西山事件のあと、苦しみの中で立ち直り、維持していった厳しさを、各紙は骨身で感じているのだろうか。
また、いろいろな角度から情報を得て、深く広く物事を考えることなく、スケッチ的な短行の見出し文化の風潮が進行して、活字離れ、活字に触れなくてすむような社会状況もある。
そして、記者の成り手の減少、記者育成の手立ての甘さ、経営の厳しさから初期の記者育成という課題が重視されていない現実など、考え込まざるを得ない姿がある。
*「朝日」はヒダリか? 朝日は左翼だ、という宣伝がいまだに、まことしやかに流されている。実態を踏まえない、つまらぬプロパガンダなのだが、そのように思い込ませる効果はある。しかし、メディアの生まれる基本は、権力を握るものを監視し、誤りそうな方向を指摘し、恣意的な姿勢を批判し、国民・住民サイドに立つ姿勢である。ウソ・フェイトの宣伝はやめとけ!と言いたいが、それで売り、食っていくメディア産業や人物がいる以上、攻撃に耐える力も必要だろう。
だが、かつての朝日は、あえていうならミギに近く、権力に迎合しすぎてきてはいないか、との印象すらある。言論人でありながら、終盤になって権力者サイドに動き、活躍した緒方竹虎、河野一郎、橋本登美三郎、細川護熙らがいる。その姿勢が悪いとは言わないが、ミギ寄りだという指摘も否定できない。
さらに言えば、戦前の翼賛政治下の元新聞記者の立場からは、その姿勢がよく見えてくる。
翼賛政治体制下の政治家として、その方針で動いた人物を拾うと、小山松壽、一宮房治郎、清瀬規矩雄、伊豆富人、春名成章、池田秀雄、神尾茂、頼母木真六らがいるし、中野正剛も一時は翼賛体制に近づいていた。
これが「ヒダリ」の新聞社なのか。この事実に目を向けずにアピールするセンスもさることながら、言われるがままに信じやすく、騙される側もおかしくないか。
*怖さとはなにか 戦後も生き残った政治家で、翼賛がらみの人物には、河野一郎、河野密、野田武夫、羽田武嗣郎、高橋円三郎らがいる。それぞれの言い分があることは分かるが、重大局面に臨んだ時が政治家の生命線だとするならば、彼らは明らかに権力志向・権力容認・権力迎合と思われてもやむを得ない経歴を持つ。彼らは、政治家として活動していたとき、終戦の事態に臨んで、戦前の姿勢との切り替えや反省をどのように説明したのだろうか。
政治家が時代の局面で右往左往していいのか、かくあれかしの社会を目指したはずの言動が急激に反転したことを国民に示してきたか、その責任は問われざるを得ないだろう。
良くも悪くもメディアに対する「批判」以上の攻撃的宣伝は止むを得ない。だから、それらの情報源を知り、背後のうごめきを感知しておく必要がある。反論も必要だ。政治家についても、過去・現在・未来の言説の変化を見抜き、うまい言葉とその内実の矛盾を知る努力の習性がないと、騙されかねない。あるとき気付いたら、目の前に予想外の世界が展開され、その苦しみの渦中に身を置かざるを得ないことにもなる。
敢えていうなら、多数決という民主主義システムの怖さである。
*左翼側の人材は? 戦前の無産政党に生き、戦後の時代にもその世界観をアピールしたスジ者として生きた人たちもいる。それが、良いということではなく、名を挙げて見れば大山郁夫、鈴木文治、風見章、河野密、田原春次、聴涛克巳、秋山長造、戸叶武らがいる。それぞれに揺らぎもあったようだが、普通ではなかなかできにくい立場を貫いたといえるのだろう。
朝日にその程度の自由はあったのか、と改めて感じる。弾圧のもとで、おのれの正しいと信じることを言い続けることは、それほど容易ではない。まず、おのれ自身との闘いがあり、大きく流れる社会に反旗を翻す論理や自信が必要だ。権力のかけてくる圧力の、精神的な負担は想像以上だろう。よくぞ耐え抜いたものだ、と感心する。普通にはできない希少な存在だった。
このような人材を派出した朝日であるから、「アカイ朝日」「ヒダリの朝日」と宣伝したいのだろうが、そう甘いものではない。出所不明の攻撃を仕掛けてきたり、街宣車などでアピールに余念のないグループがいたり、さまざまながら、実際にあった歴史と、その裏側をよく見てほしい。
*結論的には あまり言うことはなく、別添の記録を読み取ってほしい。時代は動き、流れは変えられる。権力者は、重要な局面になると、正当化する材料を巧みに使い、知られたくない事実を隠したり、言葉の巧みさでごまかしたりする。異論を唱える論者や集団を無視し、聞こうとしない。議論を避け、応じても正面からの応酬をせず、別の口ぶりで逸らす。新聞の機能は、これを見抜くところにある。
言論の自由のもとにある新聞記者の軌跡を追うと、民主主義のありようは難しく、だましだまされやすく、権力を監視するはずのメディアが権力サイドに呑み込まれていく容易さを感じざるを得ない。
*育て、新聞記者たち 元新聞記者から見て、優れた記者は今も決して少なくない。信念を持って、この世界に入ってきた有能な人々に出会うことも多い。どの新聞も、どのテレビも、というほどの自信はないが、身近に感じる限り、そのような人材は決して少なくはなく、懸念もない。
ただ、活字企業の現状は厳しい。さまざまな情報について、活字を読み、選別し、おのれの判断を下し、自分の見解を迷いつつも固めていく作業を好む読者が減りつつある。
部数と広告量が支えてきた新聞は今、部数の減少、広告の他メディアへの移行によって、経営難に置かれている。経営陣の苦悩は、さまざまな経費削減策のなかで、次第に人減らしに向っている。そのことが、有能な記者の志望を減らし、各人の時間的ノルマが増し、自己研修や知識の蓄積、足による取材などを制約してくる。コストのかかる企画や、長期にわたる調査報道の力を弱めかねない。
ことは新聞ばかりではない。
テレビで流される情報には、望ましいセンスや新鮮な切り口が見られる一方、おかしくもなく語り続け、品のなさで売るようなお笑いや芸能人らの登場が目立ち過ぎている。機器による情報手段も、短行による応酬ばかりで、ものごとの事態を多角的に見て論議する習慣が薄れてきている。社会の流れは「いいね!」では済まされない。
だから、活字を、とまではいわないが、これからの時代を長く、深く、丁寧に見続け、外国を含む相手と分かりあえる交流を続けていくメディアの機能を考えなければならないだろう。
戦前戦後の新聞記者たちの振る舞いように触れて見て、少し風呂敷を広げすぎたようだ。
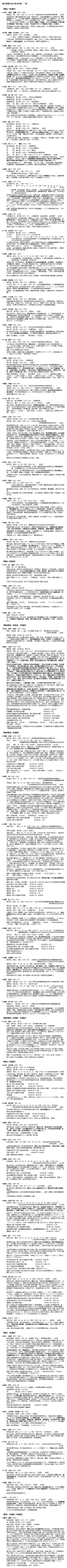
(元朝日新聞政治部長)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧